【中学受験・小4】植木算の指導で見落としがちな4つの原因

算数の中でも「植木算」は、一見するととてもシンプルな単元です。
「木を何本植えるか数えるだけの話でしょ?」と、大人からすれば簡単に思えるかもしれません。
ところが実際には、多くの小学生がここでつまずきます。
「式はわかっているのに答えが合わない」
「言われれば理解できるけど、自力で考えられない」
そんな声を、保護者の方からもよく耳にします。
なぜ、これほど“単純そうな問題”で子どもたちは立ち止まってしまうのでしょうか?
実はそこには、大人が見落としがちな 発達段階の壁 や 言葉の理解の難しさ が潜んでいるのです。
この記事では、子どもが植木算でつまずく代表的な原因を4つ取り上げ、指導の工夫や考え方をお伝えします。
「簡単な単元ほど指導が難しい」と言われる理由が、きっと納得できるはずです。
①実際に木を植えて考えないから
中学受験において、植木算を学習するのは4年生の前半であることが多いです。
塾によって多少カリキュラムに差はありますが、おおむね4年生の前半です。
この時期の子供は、発達段階的に、まだ具体的思考の段階です。
抽象的な思考、つまり紙の上だけで考える事はまだ得意ではない時期です。
子供が「600mの道」という文字を見たときに、頭の中に600mの道は浮かんでいないかもしれません。
ただ文字情報としての「ロッピャクメートルノミチ」という情報しか入っていない可能性があります。
そんな子に「状況をイメージして!」と言ったところで無意味です。
状況のイメージとは何なのか、それが分かっていないのでイメージのしようがありません。
4年生の前半とは、まだ言語によるコミュニケーションが不完全な時期です。
日常の事柄や、目の前にある物体を説明することは可能ですが、目の前にない物や空想上のもの(「40本の木」や「15個のリンゴ」など)を言葉を通してコミュニケーションすることが苦手な子も少なくありません。
そんな子に対して、算数の指導をするのですから、おのずと手段は身体的経験の重要性が高まります。
言語で「20mの道に4mおきに木を植えるんだから、間が5個で~」のように説明しても、適切ではありません。
言語を通して、目の前にない物を理解できるようになるのはまだ先の話です。
ではどのように指導すればいいのか?
実際に木を植えてみるしかありません。
木を植えるのは大変ですから、何かペンなどを教室の床に並べて、実際に物体を見せることで理解を醸成します。
4年生前半の子への算数指導は、紙と鉛筆に頼っていてはいけません。
出来るだけ目に見えるモノを通して指導するようにしてください。
②名づけを軽視しているから
人間がモノを認識する際、名前がついているかどうかは大切です。
名前が付いた瞬間に、急に見やすくなることは良くあります。
例えば「スマホ指」という言葉があります。
現代人はスマートフォンを片手で持つことが多いので、重みで小指の骨が曲がってしまう現象のことです。
今まで他人の小指が曲がっているかどうかなんて気にしたことが無かったと思います。
でも、今この言葉を知った読者の方は、今後は小指が変形している人を見かけた際に「あ、スマホ指だ」と認識できるようになったと思います。
言葉を知ったおかげで、見えにくかったモノがよく見えるようになるという一例でした。
さて、植木算にはとても見えにくいモノが登場します。
「あいだの数」です。
簡単に説明しますね。
例えば60mのまっすぐな道に、端から端まで4mおきに木を植えた場合。木は何本でしょうか?
答えは15本ではありません。
60÷4=15 の計算で求められる”15”は、あいだの数です。
4mという間隔が15個ありますが、木の本数は16本が正解です。
さて、「あいだが何個あるか?」と言うのが小学生には認識しづらいです。
「あいだ」という、木と木の真ん中にある無の空間に対しての呼称だからです。
無の空間に名前を付けるという行為は、割と高度な知的営みだと思います。
小学4年生にとっては、まだ直観的に理解しにくいことなのだと思います。
でも、どうにかして4年生でも理解できる形で「無の空間に名前を付ける」ということを説明したいですよね。
何か良い例は無いか……
ありました!!! 最適な例があります。
「ドーナツの穴」です。
ドーナツの穴という言葉は、無の空間に対してつけられた名前です。
何もない空間に対して「そこにはドーナツの穴がある」なんて言います。
なかなかオシャレな言葉じゃないでしょうか?
植木算を始めて学習する小学生にも、ドーナツの穴の話を良くします。
雑談を通して、無の空間に名前を付けるという行為を理解してもらい、その後で、木と木の中間に存在する無の空間に対して「あいだ」という名前を付けているのだと説明します。
(「あいだ」が無機質で馴染みにくければ「謎の空間」とかでも良いです)
とにかく、植木算では無の空間に対して名前を付けて、あまつさえその個数を数えているのだと。
そんなことを「ドーナツの穴」という例を通して認識してもらう。
そんな風に指導を展開してみるといいかもしれません。
③わり算が分かっていない
そもそもわり算が分かっていない可能性も疑ってみましょう。
「わり算なんて分かってるよ!」と思われるかもしれませんが、ちょっと待ってください。
わり算には大きく二つの意味(使用状況)があります。
ひとつは「60個のリンゴを3人に分けます。一人何個もらえますか?」のような場合。(等分除)
もう一つは「60個のリンゴを、一人につき3個ずつ配ります。何人に配れますか?」のような場合です。(包含除)
大人からすると、どっちも同じやん! と思うかもしれませんが、小学生にとっては別物のように思えているかもしれません。
そして多くの場合、前者の「3人に分けます」の方は強く認識されていますが「3個ずつ分けます」の方はあまり意識されていなかったりします。
そんな子にとっては「60mの道に4mおきに木を植えます」が「60÷4」であると思えないかもしれません。
これはあくまで一例ですが、子供が分からなくなる原因はさまざま考えられます。
ただ正しい解き方・正しい式を教え込めば出来るようになるという訳ではありません。
正しく教えているはずなのに、子供が全然出来るようにならない場合は、思いもよらない弱点が見過ごされている可能性が高いです。
やみくもに暗記しろと強要するのではなく、適切な指導者に相談するようにしてください。
お子様の反応や解いた跡から、分からなくなっている原因を探ってもらうようにしましょう。
④言葉を知らないのかも?
番外編として、単語の意味が分かっていない可能性も疑ってみましょう。
指導の中で、実際に生徒が分からなくて困っていた単語を以下に紹介します。
両端:両方の端のこと。つまり右端と左端のこと
くい(杭):地面に刺さった木の棒のこと。ロープを結んで、柵のようにする
ごと・おき:「4mごとに木を植えます」や「4mおきに木を植えます」のように使う。
まとめ:簡単な単元ほど指導は難しい
簡単な単元であるほど、指導は難しいです。
6年生で学習する複雑な旅人算の問題などは、解くのは大変ですが指導はそこまで大変ではありません。
生徒が、何を分かっていて何を分かっていないのかがある程度予想がつくからです。
一方で、初歩的な単元(和差算・植木算・周期・つるかめ算など)は指導が難しいです。
ある程度得意な生徒の指導ならば何の問題もありませんが、困っている子の指導の場合は大変です。
分からない原因はある程度パターン化は出来るものの、やっぱり最後は千差万別。育ってきた環境や発達の段階は個人差があるので、指導方法・説明方法が子によって最適な方法は変わります。
Aさんにとっていい指導法がBさんにとっても良いかどうかは分かりません。
そんな難しさを含んだ単元である「植木算」を熱く語ってみました。
保護者の皆様の参考になれば幸いです。


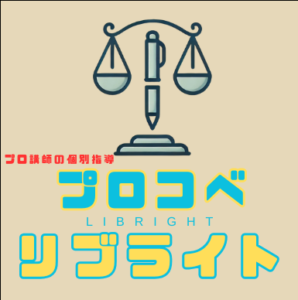


コメント